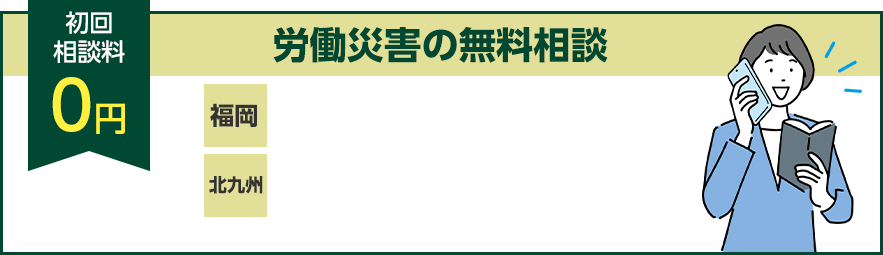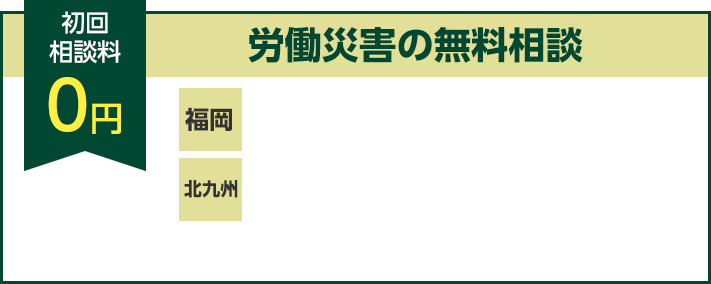うつ病等の精神疾患についても労災認定を受けられる可能性があります。
パワハラや過重労働などの業務上の原因から心理的負荷を受け、うつ病等の一定の精神疾患を発病してしまった場合にも、労働災害(労災)と認定され、労災保険制度から給付を受けられる可能性があります。
今回は、精神疾患について労働災害と認められる要件と、その申請方法についてご案内します。
労災認定の基準
「キツい仕事をしていたところ精神疾患を発病した」と主張するだけでは、残念ながら労災認定を必ずしも受けることはできません。
精神疾患は「キツい仕事をしたこと」だけでなく、私生活のなかなどそのほかの様々な要因によって発病する可能性があるため、労災を認定されるときの審査においても「精神疾患を発症する原因となったのは本当に業務なのか」という点が非常に重要になります。
厚生労働省は、「精神疾患を発症する原因となったのは本当に業務なのか」という基準を明確にするため、精神疾患について労災認定を行う際の3つの要件を公表しています。
特定の精神疾患を発病したこと
まず、あなたが(うつ病を含む)「気分障害」、「統合失調症」などの精神疾患を発病したことが必要です。そのため、医師に精神疾患に関する診断書を書いてもらい、その記載内容によって労災認定の対象疾病を発病したことを証明します。
また、医師が病名として記載すれば必ず認められるというものではなく、診療録等の関係資料や、申請者本人・関係者からの意見聴取などを通じて事実確認を行い、総合的に発病の有無や発病時期が認定されます。
発病前に業務による強い心理的負荷があったと認められること
つぎに、発病前(6ヶ月間程度)に「業務による強い心理的負荷」があったと認められることが必要です。厚生労働省は「心理的負荷」について「評価表」を設けており、負荷の種類ごとに通常どの程度の「心理的負荷」を受けるであろうという目安を定めています。
具体的には、
Ⅰ業務の中で過失によって他人を死亡又は重大な怪我をさせてしまった、意思を抑圧されて強姦・猥褻行為を受けた、発病直前の1ヶ月に160時間以上の時間外労働を行ったなど、特に強い心理的負荷を伴うのが当然といえる出来事があった場合、原則として「強い」心理的負荷があったと認められます。
また、
Ⅱ職場で悲惨な事故があった、(慣習として行われることがあっても)本来は違法な行為を強要された、達成困難なノルマを課された・ノルマを達成できなかった、顧客・取引先から無理な注文を受けた、といった場合には、それだけで必ず「強い」心理的負荷と評価されるわけではありません。それぞれの出来事についての具体的な事情や、各事情が関連する程度を考慮した上で、「強い」心理的負荷といえるかが判断されます。
なお、最近話題になることが多い長時間労働がある場合は、上記の「発病直前の1ヶ月間に160時間以上の時間外労働を行った場合」以外にも、
・発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行った場合
・発病直前の2ヶ月間連続して1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った場合
・発病直前の3ヶ月間連続して1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合
・転勤して新たな業務に従事し、その後月100時間程度の時間外労働を行った場合
などが「業務による強い精神的負担」として例示されています。
業務以外の心理的負荷・個体側要因により精神疾患を発病したものではないこと
さいごに、「業務以外の要因で発病したとはいえないこと」も必要とされています。②の要件と同様、出来事の種類ごとに、受けるであろう心理的負荷の評価表が作成されています。
たとえば、業務とは無関係に、配偶者と離婚した、家族が死亡・重い怪我を負った、流産してしまった、犯罪に巻き込まれたなど、それだけで強い心理的負荷を受けるであろう出来事があった場合、「業務以外の心理的負荷」によって発病したと評価されやすくなります。
また、もともと精神疾患を患っていた、アルコール依存症であったなど、もともと精神疾患を発症しやすい方については、業務が原因での発症であるかどうかについて慎重な判断がなされます。
もっとも、私生活が順風満帆という状況でなかったとしても、あくまで精神疾患になった主原因は業務上受けた心理的負荷であるとして、労災と認定される可能性もあります。
他にも原因が考えられるからといって簡単に諦める必要はありません。